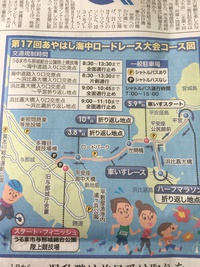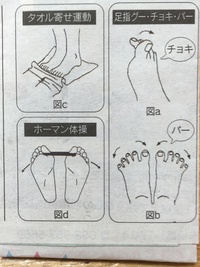いろんな病気について
注意したい病気「肝硬変」[44]
ハイサイ!!!
T.Tです♪♪
今日は注意したい病気「肝硬変」の種類と症状、予防について紹介します。
◎肝硬変とは
肝硬変とは、肝臓の炎症(肝炎)の繰り返しにより肝臓が硬くなって委縮し、肝臓の代謝や解毒などといった生命維持に欠かせない機能が十分に働かなくなった状態です。悪化すると、肝脂肪がんに進行してしまうこともあります。
●肝硬変の種類と症状
肝硬変には、ウイルス性肝硬変やアルコール性肝硬変などがあります。
ウイルス性肝硬変はB型、C型などのウイルス性肝炎による慢性肝炎が原因で起こるものですが、アルコール性肝硬変は長期間の過剰な飲酒が原因で発症するので、生活習慣と関連が深い病気と言えます。
主な症状は、男性では、ED(勃起不全)、性欲減退、女性では月経不順がみられることがあります。
◇肝臓に優しい生活を◇
肝臓は別名「沈黙の臓器」と呼ばれます。その理由の第1は、多少にダメージを受けても残った細胞がカバーして働き続けるタフさ。第2は、感覚が鈍いために悲鳴をあげられない知覚神経のなさ。第3は、7割を切っても1年でもとに戻る再生力です。
このタフさが裏目にでてしまう結果、自覚症状が現れにくいのです。自覚症状が現れても放っておけば、多くの場合、肝硬変に移行します。完治不可能な肝硬変に至る前に、肝臓に優しい生活を始めましょう。
☆肝硬変の予防ポイント☆
ポイント1 お酒は控える
肝硬変の原因がお酒であると疑われる場合は、すぐに禁酒をする。禁酒が無理でも、量を減らしたり、週に2~3日は禁酒日を設けたりする努力が必須。
ポイント2 食生活を見直す
添加物の多いインスタント食品やスナック菓子などのような食品は肝臓に負担をかけるので、摂りすぎないようにする。
ポイント3 栄養バランスを考えた食事を心がける
主食や主菜、副菜のバランスを考え、できるだけ栄養に偏りのない食生活をする。高たんぱくの食事は肝機能を高める
ポイント4 野菜類を積極的に摂る
肝臓の働きを助けるビタミンやミネラルを多く含む野菜類を積極的に摂るようにする。
ポイント5 不規則な生活を改める
睡眠不足や過労が重なっているときは、肝臓の機能も働きっぱなしになっているので、規則正しい生活に改め、肝臓をゆっくり休ませる。
ポイント6 肥満に注意する
肝硬変は肥満から脂肪肝を経て発症することがあるので食べすぎなどに注意する。
ポイント7 適度な運動する
1日30分のウォーキングなどの軽い運動を継続して行えるようにする。
ポイント8 ストレスをためない
ストレスは肝臓の大敵! 日常生活の中で上手にストレス解消出来るようにする。
ポイント9 健康状態をチェックする習慣をつける
肝硬変は自覚症状が少ないので、日頃から健康診断などで脂質異常症のチェックをする。
![注意したい病気「肝硬変」[44]](//img01.ti-da.net/usr/churaumikenkouin/IMG_0364.JPG)
肝硬変は悪化すると肝細胞がんに進む非常に怖い病気です。ですから、肝硬変になってしまう前の予防が大切です。日常生活をチェックしましょう。
T.Tです♪♪
今日は注意したい病気「肝硬変」の種類と症状、予防について紹介します。
◎肝硬変とは
肝硬変とは、肝臓の炎症(肝炎)の繰り返しにより肝臓が硬くなって委縮し、肝臓の代謝や解毒などといった生命維持に欠かせない機能が十分に働かなくなった状態です。悪化すると、肝脂肪がんに進行してしまうこともあります。
●肝硬変の種類と症状
肝硬変には、ウイルス性肝硬変やアルコール性肝硬変などがあります。
ウイルス性肝硬変はB型、C型などのウイルス性肝炎による慢性肝炎が原因で起こるものですが、アルコール性肝硬変は長期間の過剰な飲酒が原因で発症するので、生活習慣と関連が深い病気と言えます。
主な症状は、男性では、ED(勃起不全)、性欲減退、女性では月経不順がみられることがあります。
最初はあまり自覚症状はない
↓ 徐々に進行が進む
吐き気や脱水、腹部膨満感、倦怠感や疲労感が現れる
↓ さらに進行する
親指や小指の付け根が赤くなる「手掌紅斑」
胸に「クモ状血管腫」
皮膚が黒ずむ
男性は女性ホルモンの影響で胸がふくらむことも
↓ ますます進行する
意識障害や腹水、黄疸、足のむくみなどが現れる
↓ そして...
食道静脈瘤などで吐血することも!!
↓ 徐々に進行が進む
吐き気や脱水、腹部膨満感、倦怠感や疲労感が現れる
↓ さらに進行する
親指や小指の付け根が赤くなる「手掌紅斑」
胸に「クモ状血管腫」
皮膚が黒ずむ
男性は女性ホルモンの影響で胸がふくらむことも
↓ ますます進行する
意識障害や腹水、黄疸、足のむくみなどが現れる
↓ そして...
食道静脈瘤などで吐血することも!!
◇肝臓に優しい生活を◇
肝臓は別名「沈黙の臓器」と呼ばれます。その理由の第1は、多少にダメージを受けても残った細胞がカバーして働き続けるタフさ。第2は、感覚が鈍いために悲鳴をあげられない知覚神経のなさ。第3は、7割を切っても1年でもとに戻る再生力です。
このタフさが裏目にでてしまう結果、自覚症状が現れにくいのです。自覚症状が現れても放っておけば、多くの場合、肝硬変に移行します。完治不可能な肝硬変に至る前に、肝臓に優しい生活を始めましょう。
☆肝硬変の予防ポイント☆
ポイント1 お酒は控える
肝硬変の原因がお酒であると疑われる場合は、すぐに禁酒をする。禁酒が無理でも、量を減らしたり、週に2~3日は禁酒日を設けたりする努力が必須。
ポイント2 食生活を見直す
添加物の多いインスタント食品やスナック菓子などのような食品は肝臓に負担をかけるので、摂りすぎないようにする。
ポイント3 栄養バランスを考えた食事を心がける
主食や主菜、副菜のバランスを考え、できるだけ栄養に偏りのない食生活をする。高たんぱくの食事は肝機能を高める
ポイント4 野菜類を積極的に摂る
肝臓の働きを助けるビタミンやミネラルを多く含む野菜類を積極的に摂るようにする。
ポイント5 不規則な生活を改める
睡眠不足や過労が重なっているときは、肝臓の機能も働きっぱなしになっているので、規則正しい生活に改め、肝臓をゆっくり休ませる。
ポイント6 肥満に注意する
肝硬変は肥満から脂肪肝を経て発症することがあるので食べすぎなどに注意する。
ポイント7 適度な運動する
1日30分のウォーキングなどの軽い運動を継続して行えるようにする。
ポイント8 ストレスをためない
ストレスは肝臓の大敵! 日常生活の中で上手にストレス解消出来るようにする。
ポイント9 健康状態をチェックする習慣をつける
肝硬変は自覚症状が少ないので、日頃から健康診断などで脂質異常症のチェックをする。
肝硬変は悪化すると肝細胞がんに進む非常に怖い病気です。ですから、肝硬変になってしまう前の予防が大切です。日常生活をチェックしましょう。
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。